「対人関係」の悩みとして相談室に持ち込まれるものの一つに、「職場での部下や後輩への関わり方」についての相談があります。
このような相談の中から、「部下や後輩に指示や命令を出すことの“評価”」について考えてみたいと思います。

今回は特に、「“手腕”と“手法”を区別すること」に焦点を当てて、あるバスケットボール監督を例に引きながら、検討しています。
参考にして頂ければと思います。
はじめに。
職場で業務を遂行するために、部下や後輩に指示や命令を出すということは、上司や先輩の立場になれば、当然求められるものです。

「自分が今この場面で、部下や後輩に対して、どう関わればよいのだろうか?」と言うことを、あなたも指導的な立場に就けば、当然考えることでしょう。
また、部下や後輩に対して自分がとった言動が、自分の上司からどのように“評価”されるかについても気になるところです。
このような「対人関係に関わる“問題”」に対しても、このブログの中ですでに取り上げた、「問題が解決するための“7つのステップ”を知っておきましょう。」のタイトル記事で紹介した「方法」が、参考になると思います。
ただし、「対人関係」と「その“評価”」に関しては、新たに認識すべき事柄があります。それは、「“手腕”と“手法”を区別して考えてみる」と言うことです。
今回はこのことについて、考えてみたいと思います。
あるバスケットボール監督のこと。
今回の問題を検討するにあたり、取り上げたい人物がいます。それは、2021年の東京五輪で女子バスケットボール日本代表を率いて、チームに銀メダルをもたらしたトム・ホーバス監督です。

トム・ホーバス監督と言えば、女子日本代表選手に対して、「何やってるんですか!」と大声で怒鳴りつける「怖い監督」として、当時のワイドショーでも取り上げられていたので、ご記憶の方も多いのではないでしょうか。
「徹底的な細部へのこだわり」をする監督なのだそうで、それを女子選手に指摘するときの言葉が、あの「何やってるんですか!」と言う一喝(いっかつ)だったのでしょう。

そんなトム・ホーバス氏が、東京五輪が終わった後、次のパリ五輪に向けて、今度は男子日本代表チームの監督に就任するという報道が流れました。
私はスポーツに関しては全くの素人ですので、このニュースを知ったとき、「トム・ホーバス監督が、あの“何やっているんですか!”と言う言葉を“武器”に、今度は男子選手を厳しく鍛え上げるのだろう」と思いました。

その後、パリ五輪に向けての話題が徐々に高まるにつれて、テレビでもオリンピック特集が組まれるようになりました。男子バスケットボールもメディアで取り上げられるようになり、練習風景や試合結果が報道される機会も増えてきました。
ところが、メディアで流されたどの映像を見ても、トム・ホーバス監督が男子選手に対して、例の「何やってるんですか!」と檄(げき)を飛ばすシーンはありませんでした。
これはとても不思議なことでした。
満島真之介さんによるバスケットボール解説。
男子バスケットボール日本代表チームは、2024年パリ五輪でメダルを獲得するために、オリンピック出場権をかけたワールドカップ順位決定リーグで、絶対に勝ち抜けなければなりませんでした。
男子日本代表チームは、このリーグ最終戦で西アフリカのカーボベルデを破り、悲願のパリ五輪出場権を獲得しました。自力での出場権獲得は、モントリオール五輪以来、実に48年ぶりだったそうです。

このニュースは、2023年9月初秋の日本列島を駆け巡りました。実際、試合の翌日、テレビ朝日の「羽鳥慎一モーニングショー」でも特集が組まれていました。
その番組ゲストコメンテーターとして出演されたのが、俳優の満島真之介さんでした。このときの満島さんの解説に、私はとても納得させられました。

満島さんによりますと、男子日本代表チームは、日本や海外のクラブで活躍する日本のトップ選手を、これまでも招集して国際大会に臨んできたそうです。
しかし日本チームは、どうしても背の高い海外チームに“圧倒”されてしまい、本来持っている力を選手が十分に出し切れないまま、大会が終わってしまうということが、これまでの“繰り返し”だったと言います。
満島さんによれば、今回ワールドカップ大会が開催されるにあたって、NBAの所属選手はその活動期間が大会直前の最大28日までと、労使協定で決められていたそうです。そのため、NBA選手を多く抱える海外チームは、今大会の開会前に代表メンバーを招集して、長期の合同練習を行うことが難しかったと言います。

ところが、男子日本代表チームは、海外チームよりもかなり早い6月に合宿を組んで、合同練習を開始することができました。満島さんは、「今回の日本代表チームは、練習内容もさることながら、その練習に取り組んだ期間も“世界一”だった」と指摘していました。
さらに、「自分たちは、世界のどの国にも負けないだけの期間、あの練習をこなしてきたのだという“自信”を胸に、日本選手は開催地の沖縄に乗り込んでいた」と、満島さんは解説されました。
トム・ホーバス監督の「変化」。
長期合宿練習によって「自信」を獲得できた男子日本代表選手を監督するにあたって、トム・ホーバス監督が直面した問題は、「どうしたらこの“自信”を、男子選手がワールドカップ大会期間中、ずっと持ち続けられるだろうか?」と言うことではなかったかと、満島さん推測されていました。
その答えが、「“何やってるんですか!”と言う女子選手に使っていたあの有名な言葉を“封印”し、男子選手代表に対しては使わないという決断だった」と。

満島さんは、「今回、試合中にホーバス監督は男子代表に対して、“信じなさい”、“自信を持って”、“信頼して下さい”と言う“言葉”を多用していた」と指摘されました。
確かに、あの「何やっているんですか!」と言う言葉を、監督から試合中に男子選手がたびたび浴びせられてしまったら、ようやく培われた選手の「自信」など、一気に押しつぶされてしまい、選手はみんなシュンとなってしまったことでしょう。
ホーバス監督が今回多用した「信じなさい」「自信を持って」「信頼して下さい」と言う言葉は、「男子選手の“自信”を下支えするための言葉だった」と言えるでしょう。
満島さんの解説を伺い、トム・ホーバス監督の「言葉の“選択”」に、私は脱帽した思いでした。
トム・ホーバス氏は「監督としての“手腕”」を変えたのか?
トム・ホーバス氏は、東京五輪で女子日本代表チームに銀メダルをもたらしました。この実績が評価されて、今度は男子日本代表監督に就任したのではないでしょうか。
この出来事を私たちは、次のように表現したりします。例えば:
- 「女子代表チームの監督としての“手腕”を買われて、今度は男子代表チームの監督に就任した」と。

ところで、このような場面で「手腕」を言う言葉を使うとき、私たちはそこにどんな意味を込めているのでしょうか。「監督としての“手腕”」とは、いったい何を指しているのでしょうか。
実は私は、「怖い監督」として女子日本代表チームを監督した「指導スタイル」のことを、トム・ホーバス監督の「監督としての“手腕”」だと、このときは考えていました。
そのため、男子日本代表監督に就任するという報道に接した際も、すでに述べたように、私は「あの“何やっているんですか!”と言う言葉を“武器”に、今度は男子代表を厳しく鍛え上げるのだろう」と思ったわけです。
つまり、私はホーバス氏の「監督としての“手腕”」を、「強い言葉を“武器”に、選手を厳しく鍛え上げることができる“指導スタイル”のこと」と捉えていたのです。

ところが、男子日本代表チームを率いたときのトム・ホーバス監督の「指導スタイル」は、女子日本代表チームのときに選手に対して見せた「指導スタイル」とは、全く違うものでした。
トム・ホーバス氏がこの男女二つのチームに対して採用した「指導スタイル」の“違い”を、どのように考えればよいのでしょうか。トム・ホーバス氏は、「監督としての“手腕”」を、この間に変えたのでしょうか。
「2つの思考実験」から分かること。
ここで、ちょっとした「思考実験」をしてみたいと思います。

それは、「もしも男子日本代表チームが今回負けてしまって、パリ五輪への出場権を獲得できなかったとしたら、世間の声は、どのようなものになっていたか?」と言うものです。
もしかしたら、それは:
- 「なぜ、女子日本代表を監督したときと同じように、“何やってるんですか!”と言わなかったのか!」
- 「女子日本代表を指導したときの“指導スタイル”のように、厳しく指導しなかったから、勝利の結果が出せなかったのだ!」など、と。
このような批判の声を上げる人たちの中には、次のように考えた人も、きっといたことでしょう。
- 「トム・ホーバス氏は、『監督としての“手腕”』のない人だ」と。

さらに、もう一つ「思考実験」を行ってみましょう。
それは、「もしもトム・ホーバス監督が男子日本代表チームを指導するに際して、女子日本代表に対して採用した“指導スタイル”と同じように、『何やっているんですか!』と活を入れる“厳しい指導スタイル”で監督した結果、バリ五輪への出場権を獲得できたとしたら、世間の声は、どのようなものになったか?」と言うものです。
もしかしたら、それは:
- 「トム・ホーバス監督の“何やっているんですか!”の一喝は、どんな選手の力も引き出せる“魔法の言葉”だ!」
- 「トム・ホーバス氏は、どんなチームに対しても、厳しく指導して勝利に導ける名監督だ!」など、と。
このような賞賛の声を上げる人たちの中には、次のように考えた人も、きっといたことでしょう。
- 「トム・ホーバス氏は、『監督としての“手腕”』のある人だ」と。
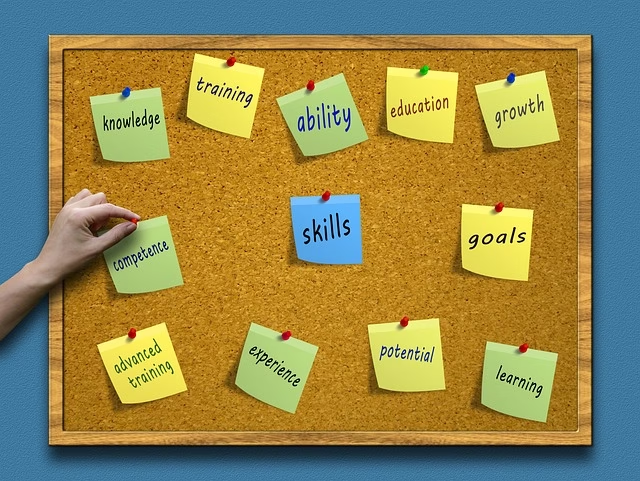
「手腕」の本来の意味は、「成果を出せる能力」のことです。
ところが、この2つの「思考実験」から分かるように、「手腕」という言葉が世間では、成果を出した人物がそのときに採用した「指導スタイル」として、捉えられてしまいがちなのです。
「成果を出した“一つの指導スタイル”を持ち合わせていること」でもって、「“手腕のある人”である」と短絡的に結びつけてしまうことは、とても危険なことではないでしょうか。
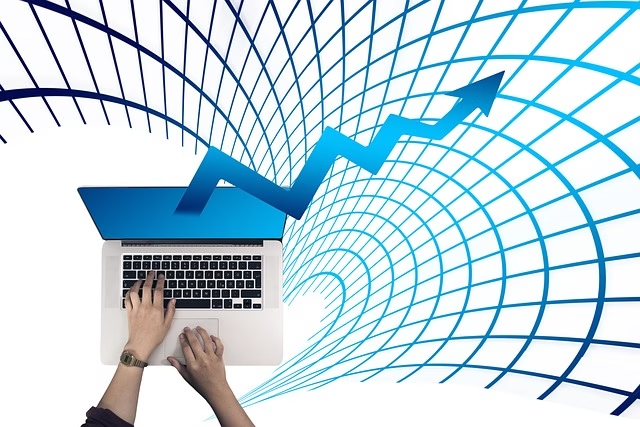
実際に私がミスを犯したように、スポーツファンの世界で称賛の声をあげる人たちも批判の声を上げる人たちも、スポーツ指導者や監督が採用した「一つの“指導スタイル”」でもって、その指導者や監督としての「手腕」を評価してしまう危険性から、免れることができないのです。
「手腕」と「手法」を区別して使ってみると…。
これまで使ってきた「指導スタイル」と言う言葉は、「手法」という言葉と基本的には同じものだと言えるでしょう。
そこで、この「手法」と言う言葉を使って、さらに「課題解決にまつわる問題」と「その“評価”」ついて、考えてみたいと思います。

早速「手法」と言う言葉を使ってみると、「女子代表チーム監督」から「男子代表チーム監督」へと転身した際に、私たちが目撃したトム・ホーバス氏の「変化」は、どのように表現できるでしょうか。例えば:
- 「トム・ホーバス監督は、女子日本代表チーム監督のときとは“手法”を変えて、男子日本代表チームを指導した」と。

さらに、「手腕」と「手法」を意図的に区別することで、今回のトム・ホーバス氏の監督としてのチーム対応の「変化」も、以下のように表現することが可能となります。例えば:
- トム・ホーバス氏は、指導するチームを勝利に導くのための「手法」を、もともと数多く持ち合わせている監督であった。
- ホーバス氏は、それら複数の「手法」の中から、女子代表チームを監督するに際しては、「何やってるんですか!」と言う「怖い監督」として選手を指導する「手法」(これを「手法A」とする)が、勝利を導くために有効であると考え、この「手法A」を採用してみた。
- その結果、女子日本代表チームは銀メダルを獲得できた。
- 女子日本代表を勝利に導いたトム・ホーバス氏の「監督としての“手腕”」が買われ、次期男子日本代表監督のオファーがトム・ホーバス氏にもたらされた。
- トム・ホーバス氏はそれを受諾し、監督に就任した。
- 男子日本代表チームを監督するにあたって、トム・ホーバス氏は、このチームを勝利に導くのための「手法」は何かと、改めて検討した。
- その結果、女子日本代表チームに対して用いた「手法A」でなく、むしろその「手法A」を封印し、別な「手法」(これを「手法B」とする)を採用することに決めた。
- ホーバス氏が新たに採用した「手法B」とは、「信じなさい」「自信を持って」「信頼して下さい」と言う言葉を多用して、男子選手の中に育まれた「自信」を下支えしていく「手法」であった。
- この「手法B」が功を奏し、今回男子日本代表チームは、オリンピック出場権を獲得することができた。
- このような成果を出せたことによって、トム・ホーバス氏の「監督としての“手腕”」は、さらに高く評価されることとなった、と。
このように、「手腕」と「手法」を意図的に区別してみると、トム・ホーバス氏が私たちに見せた男女チームに対する「対応の“変化”」が、より鮮明になるのではないでしょうか。

まとめましょう。ここで区別した「手腕」と「手法」の“違い”は、以下のようになります。つまり:
- 「監督としての“手腕”」のある人……監督するチームを、目標である勝利に導くことができる指導能力のある人。
- 「監督としてチームを目標である勝利に導く“手法”」……監督するチームを、目標である勝利に導くために活用する一つの方法。

このようの考えると、私たちが他人を“評価”する際に陥りやすい「落とし穴」が見えてきます。それは、上述の「項目4」「項目10」のところに現れたものです:
- 「ある“問題”」を「ある“手法”」を使って解決できると、「その“手法”こそが、問題を解決できる“唯一の手法”である」と、短絡的に絶対視してしまいう傾向がある。
- このような危険性は、実際に問題を解決するための「手法」を見つけ出して、解決を成し遂げた人物本人も、免れるものではない。
- 本人を取り巻く周りの人々は、問題が解決したという「結果」の時点から、その問題を解決したときの原因である「手法」へと、時間を遡(さかのぼ)って眺めてしまうものである。
- そのため、本人を取り巻く周りの人々が「その“手法”こそ、問題を解決できる“唯一の手法”である」と、短絡的に絶対視してしまう危険性は、本人以上に高いものになってしまうであろう、と。
「手腕」と「手法」とを混同する危険を回避する。
私たちが「問題解決のための“手法”」を手に入れたときに起きる、「手腕」と「手法」とを混同して考えてしまう危険性を、私たちはどのようにして回避すればよいのでしょうか。

危険回避の手順として、次のことを提案したいと思います。それは:
- ある問題を解決するにあたって、そのときにとられた「手法」は、問題解決するための「一つの手法」が、たまたま見つかっただけであると認識すること。
- ところが、ひとたび問題解決の「手法」が見つかると、人はとかく「その手法」を、「唯一絶対の手法である」と認識しがちである。
- 同時に、いったん解決策が見つかれば、「それ以外の“解決手法”があるかもしれない」と言った、解決のための「別な手法」をさらに見つけ出そうとする意欲も、急速に失われてしまうものである。
- 問題解決に対する「ただ一つの万能な手法」が、常に存在するとは限らないということを、しっかりと認識しておく必要がある。
- そのためには、仮に「ある手法」で問題が解決したとしても、「“他の手法”が存在するのではないか?」という“探求心”を持ち続けることが必須である。
- 「問題解決の“手腕”の持ち主」であることの条件には、「常に複数の解決策を見つけ出そういう意欲を持っていること」も含まれるのである。
- ところが、世間の人は、あなたが「問題」を解決できると、あなたに対して「問題を解決できる“手腕”の持ち主だ」と、短絡的に評価しがちである。
- そのため、あなたがその後に依頼された「問題」を解決できないとなると、世間の人はすぐにあなたに対して、「問題解決の“手腕”のない人だ」と批判するものである。
- あなたがこのような世間からの批判にさらされたとしても、あなたがこの批判を直ちに受け入れる必要はない。
- なぜならば、あなたは「今回用いた“手法”では、その問題が解決できなかっただけであり、他の“手法”を試すこともできるし、新たに見つけ出そうという“意欲”も自分は持っているのだ」と再認識すればよいだけのことである。
- あなたは「複数の解決手法を見つけ出そうという意欲の持ち主」であり、この様な考えの持ち主こそ、「問題解決の“手腕”のある人」なのだから、と。
まとめ。
「手法X」を採用したことで、「ある問題」を見事に解決してしまうと、「解決」という名の“成果”を出したこの人物は、世間から「万能の解決手法Xの使い手」として注目されることがあります。
評判がさらに高くなると、この人物に対して「問題解決の“手腕”の持ち主」として、世間から称賛されることもよくあることです。

このときに、「“手法X”は、数ある手法の中の“一つ”が、今回はうまく使えただけである」と考えられる人物であれば、この人物がその後に大きな“問題”を起こすことはないかもしれません。
ところが、周りからの本人への評価がうなぎ上りに高くなり、本人もうぬぼれてしまったり慢心したりしてしまうと、本来は「一つの手法」であったはずの「手法X」に対して、「究極の手法」「必殺の手法」「神の手法」などと、本人自身も考えてしまう危険性があります。
人というものはとかく、一度うまくいった「手法X」を手に入れると、それを金科玉条にしてしまい、「この手法Xなら、どんな場面でも使える“万能の手法”である」と、考えてしまう危険性から逃れられないものなのです。

「もの」や「状況」に関わる「問題」の解決であれば、「“唯一絶対”と言える解決方法」が存在するかもしれません。
そのため、自分の過去の体験に検索をかけて、その体験の中から「過去の成功事例」を思い出して、そのときに採用された「解決方法」を利用することが、ミスの少ない効率的な方法と言えるでしょう。
このことは、すでに述べたようにブログ記事:「問題が解決するための“7つのステップ”を知っておきましょう。」の中で紹介しました。

ところが、「人」を対象とした「問題」の解決場面では、一度はうまくいった「手法」であっても、それが「万能の手法」になるとは、必ずしも言い切れないのです。
あなたの採用した「対人関係場面の問題解決」の「手法X」が、世間や人事担当者から非常に高い評価を受けたとしても、あなた自身が別の場面でその「手法X」を採用する際は、さらにやらなければならない“作業”があります。
それは、新たに対象となった「部下や後輩」に対して「手法X」を使うことで、前回と同じような“成果”を出せるかどうか、また、出せているかどうかということを、施行前にもまた施行中でも十分に吟味することです。
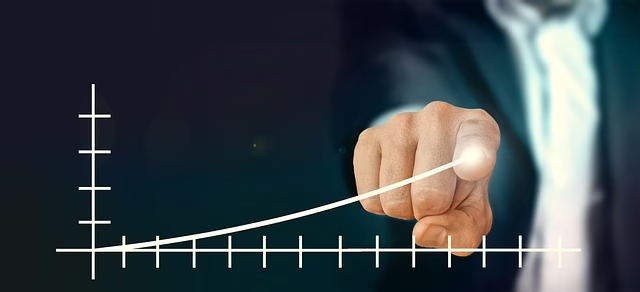
解決手法を複数持ち合わせていれば、採用した手法がうまくいかないときは、別の手法に替えればよいだけのことです。
ところが、その手法Xが劇的に成果を上げてしまったり、もともと「手法」というものを一つしか持ち合わせていなかったりすると、どうなるでしょうか。
問題が解決できていないにもかかわらず、持ち合わせの手法Xにこだわり、その手法Xを手放さず、むしろその手法Xの強度や頻度を強めて使ってしまう方向に、やみくもに進むという危険性に陥ってしまうかもしれません。

「名将」や「名監督」、「カリスマ経営者」や「●●請負人」などと称賛される人たちは、確かにその指導や経営の「手腕」が社会的に高く評価されたからに違いありません。
しかしその一方で、このような人たちの中には、その後「暴力事件」や「パワハラ問題」と言った事件で社会的に大きな非難を浴びた人物も、少なからず存在したことを見逃してはなりません。

大切なことなので、再度述べておきたいと思います。
対人関係場面で部下や後輩に関わる「問題」を解決するにあたり、自分が過去に成功した際に採用した「手法X」にこだわり、直面している事案に対して「手法X」では解決の効果を上げらていないにもかかわらず、その手法Xを手放さず、むしろその手法Xの“強度”や“頻度”を強めて対処しようとしまう方向に、一途に突き進んでしまう人物がいます。
このような人物こそ、“パワーハラスメント”を引き起こす危険性の高い人物であると、私は考えているのです。


