「マインドフルネス」と言う言葉を、耳にされた方も多いと思います。
ストレス社会を生き抜くための方法として、「マインドフルネス」が最近では様々なメディアで取り上げられたり、企業研修のテーマとして採用されたりしています。
ちなみに、Wikipeiaには、次のような記載があります。
マインドフルネス(英: mindfulness)とは、現在において起こっている経験に注意を向ける心理的な過程である。 瞑想、およびその他の訓練を通じて発達させることができるとされる。
Wikipedia
本来的に言えば、「マインドフルネス」を日々の生活の中に取り入れていく「実践」が、大切なのです。
しかし、「“マインドフルネス”とは何か?」という言う「考え方」を知っておくだけでも、自分自身の「心」の捉え方や扱い方が変わってきます。それは結果として、あなたのこれからの生き方に、大きな変化をもたらすことにもなるでしょう。

今回は、この「マインドフルネス」の「考え方」について、ご紹介致します。
「心を落ち着けたい」のに、それができない。
私たちは、今行っていることに心を向けようと思っても、それができないときがあります。むしろ、今行っていることとは全然関係ないことに、心が勝手に向いてしまうのです。
仕事に集中しなければならないときでも、その仕事に没頭できないことがあります。ふと気づくと、何か別のことを考えてしまっているのです。
ゆっくりのんびりできる機会が持てたのに、そのことを十分に満喫できないこともよくあります。入浴中にシャワーを浴びているときでも、身体を伸ばしてゆっくり湯船につかっているときでも、ゆったりとした気分になれません。心がなぜか落ち着かないのです。
職場を離れてもう帰宅しているのに、その日に職場であった嫌な出来事を、思い返してしまいます。「もう考えないぞ!」と思っても、その出来事が頭から離れないのです。
腹が立って来ることもあれば、悲しみが込み上げてくることもあります。「明日自分は職場でどうなっているのだろうか?」と、これからのことが気になり始めたりもします。そうなると、新たな不安がさらに襲ってくるのです。

自分の心なのに、その心を自分ではどうすることもできないことがあります。しかしこれは、あなたが特別だからではありませんし、ダメな人間だからでもないのです。
このようなことは、誰もが少なからず体験した覚えのあることなのです。
「心はさまようものだ」と言われても…。
「今ここ」に心を留めておくことは、確かに難しいものです。眠りに就けない夜などは、嫌が上でも、心があちこちを彷徨(さまよ)い出します。心が彷徨い出すと、気持ちは興奮し始めます。時間ばかり過ぎてしまい、眠気もどこかへ飛んで行ってしまいます。どうにもできない自分に対して不甲斐なさを感じ、さらに自分を苦しめるのです。

心を「今ここ」に留めておこうとすればするほど、心は「今ここ」つまり「現在」に留まるどころか、「これから自分はどのようになるのだろうか」と、「未来」の時空を飛び回り始めます。
その一方で、「自分がどうしてこんな風になってしまったのか」と考えたりもします。すると今度は心が、「現在」を飛び越えて、「過去」の時空に向かって彷徨い始めるのです。
「“今”を生きろ!」と言われるけれど…。
「時間」は本来、「過去」から「現在」を経て「未来」へと、流れていくものです。私たちが生きているというのは、この時間という「流れ」の中を、生きているとも言えるのです。
流れる「時間」の中を「生きている」ということは、「ろうそく」に点灯された「炎」に例えると、分かりやすいかもしれません。
たくさんの「ろうそく」が、一列にずっと並んでいるとしましょう。今その中の一本のろうそくだけに、火がついています。この一本のろうそくの「炎」が隣のろうそくを点火すると、自身の炎は消えてしまいます。「炎」は次のろうそくに移り、常に一本のろうそくだけが点灯しています。
一直線に並んだろうそくの上を、「炎」が順にリレーされていくようなイメージです。

流れる「時間」の中を私たちが「生きている」と言うことを、一直線に並んだろうそくに沿って、「炎」が次々に点灯していくものとして、眺めることができるかもしれません。
すでに隣のろうそくに点火してしまって、消えているろうそくたちが「過去」になります。これから炎が点灯するのを待っているろうそくたちが「未来」です。そして、「炎」を上げているこの「一本のろうそく」こそが、「今ここ」にあたる「現在」を示しています。
しかし本来、「今ここ」つまり「現在」は、両手をパンと叩いた、この「一瞬の“とき”」です。ろうそくの「炎」も、両手を叩いた「この一瞬」という短い時間で、隣のろうそくへと順に移っていきます。
「今ここ」は「一瞬のとき」です。点灯した「炎」と同じように、「今ここ」も「その一点」にしかありません。「その一点」は、広がりなどと言った「領域」を持たないのです。
「今ここ」にある「心」は、「広い領域」を彷徨うことなく、次々に現れては消えていく「今ここ」という「一点」に留まります。「今ここ」にある「心」は、「この一点」から「次の一点」へと、ただ瞬時に移っていくだけなのです。
まとめましょう。「心」が「今ここ」にあるとは、「炎」が隣のろうそくへと次々に移って行っても、「一本のろうそく」に「炎」が点灯した「その一瞬」に、「心」があることを言うのです。
「心」が「今ここ」にある、つまり、その「一点」に留まている限り、「心」があちこちを彷徨うことはないのです。
「健康な心」と「弱まってしまった心」
大切なことなので、再度確認しましょう。心が瞬時に移ると言っても、心は次々に現れる「今ここ」の「一点」に、常に留まっています。心はあくまで、その時々の「一点」に留まっていて、あちこちを彷徨ったりしないのです。
「心」があちこち彷徨ったりしないからこそ、「心」は無駄なエネルギーを使わないで済むのです。心が「今ここ」に留まれることを「心が健康な状態である」と言うのは、そのためかもしれません。
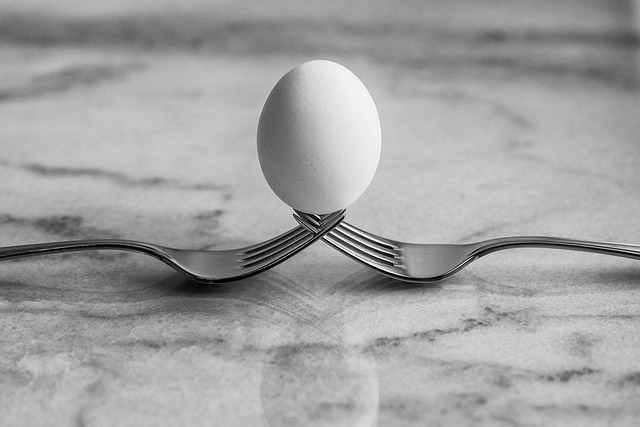
心が弱まってしまうと、「今ここ」という「現在」が、「一点」ではなく非常に広い「領域」になってしまっています。いやむしろ、心がさまよえるような「広い領域」を持ってしまっているために、その「広い領域」の中を、心が自由に駆け巡れてしまうのでしょう。
広い領域を心が駆け巡ってしまった結果、心がエネルギーを消耗し、心が弱まってしまったとも言えるのではないでしょうか。
「心を弱められてしまった人」の中には、「今」という「現在」が、「過去」の方向に広がってしまって、心がさまよえる「広い領域」を持ってしまった人もいます。
その一方で、「未来」の方向へ「今ここ」という「現在」が広がってしまって、心がさまよえる「広い領域」を持ってしまった人もいるのです。
「うつ傾向」の強い人にとっての“今”
「あの時、何で自分はあんなことをしてしまったのか?」と、自分自身の「過去のある出来事」を思い出してしまうことがあります。しかし、その出来事は、過去のある「一点」で起きた出来事です。過去の「一点」と現在の「一点」とは、本来別のもののはずです。
ところが、「うつ傾向」が強くなると、その「過去の一点」のことで、「今」もクヨクヨと悩んでしまうことがあります。「あの時、何で自分はあんなことをしてしまったのか?」と言うことを、「今」悩んでしまうのです。
こうなると、「あの出来事が起きた“過去”の時点」から「今クヨクヨと悩んでいる“現在”の時点」までが繋がってしまいます。この繋がった領域すべてが、うつ傾向が強い人にとっての「“今”という“とき”」になります。
うつ傾向の強い人にとっては、「今ここ」が「一点」ではなくなってしまったのです。「過去の方向」に向かって広がった領域すべてが、うつ傾向の人にとっての「今」なのです。
「うつ傾向」が強くなってしまっている人にとって、「“今”という“とき”」が、過去の方向に向かって広がってしまっていると言うのは、このことを言っています。

まとめましょう。うつ傾向の人の「今」は、本来言うところの両手を叩いた「一瞬の“今”」ではありません。過去に向かって広がってしまった領域としての「今」を持っているのです。その結果、この広がってしまった「“今”という“とき”」の中を、心が彷徨い巡ってしまうことになります。
「うつ傾向」の人には、「“過去の出来事”を、“現在”に蘇らさせずに、“過去”にする作業」が必要なことがあります。
私はこれを、過去の出来事を「過去に“置く”作業」と呼んでいます。
「不安傾向」の強い人にとっての“今”
「不安傾向」が強くなってしまっている人にとっての「今」とは、どのようなものなのでしょうか。この人たちにとっては、「“今”という“とき”」が、未来の方向に向かって広がっていることがあります。
「不安傾向」の強い人は、「これからどうなるのだろうか?」「もしも、こんなことが起きたら、その後どうしたらいいのだろうか?」といった、まだ現実には起きていない「将来」のことを、「今」この時点で予想して、不安感をさらに強めてしまうことがよくあります。
このような不安を心理学では「予期不安」と言います。不安そのものを先取りしていますから、「先取不安」と呼んだりもします。
「予期不安」にさいなまれている人は、「将来こんなことが起きてしまったら、その時自分は対応できるのだろうか?」と言った未来の出来事についての判断を、今現在の時点で行おうとして悩んでいます。まだ何も起きていない将来のことなのに、そのことで今不安に駆られているのです。
「予期不安」に代表されるように「不安傾向」の強い人にとっても、「“今”という“とき”」は、両手を叩いた「この一瞬」ではありません。「ある出来事が起きるのではないかと予想した“未来”の時点」と「その出来事について思い悩んでいる“今”の時点」が、やはり繋がっています。
「不安傾向」の強い人は、将来起こるであろうある「一点」のことで、今悩むわけですから、「未来の一点」とそれを悩んでいる「現在の一点」を繋げた広い領域が、この人たちにとっては、すべて「今ここ」の領域になっているのです。
まとめましょう。「不安傾向」の強い人の「“今”という“とき”」は、「現在」の時点から不安を予想した未来方向に広がっています。この未来方向に広がってしまった「今」の領域の中を、「不安傾向」の強い人の「心」は彷徨ってしまうのです。

「不安」と言うものを、「空に浮いた雲」のイメージで考えることができます。不安傾向の強い人にとっては、入道雲がどんどん膨らんでいくように、一つの不安な事柄がどんどん大きくなり、そのことでさらに不安が募ってくるのです。
「不安傾向が強い人」に対しては、その人の抱える「不安の“雲”」が大きくならないように、「不安の“雲”」に輪郭線を引いて、その輪郭線の中に「不安」を閉じ込めてあげると、抱えていた不安がそれ以上大きくならず、場合によっては不安そのものが軽減されることもあります。
私はこれを「不安に“輪郭線”を引く作業」と呼んでいます。
「集中」させるための「2つの方法」とは?
心に沸き起こる雑念を振り払いたいときや、一つのことに気持ちが集中できないときに、私たちはどうするでしょうか。きっと「集中するぞ! 集中するぞ!」「集中だ! 集中! 集中!」と言った言葉を発して、自分に「集中すること」を言い聞かせるのではないでしょうか。
心に雑念が湧いたり、何かに集中できなかったりすることは、現代人だけが抱えている問題ではありませんでした。今から2600年ほど前、仏教の修行をしている人たちにとっても、「修行に集中するためにはどうすればよいか?」と言うことは、大きな問題でした。

この問題を解決するための方法が、いろいろと考えられました。その中で、雑念が沸いてしまう心を修行に集中されるための方法として、大きく「2つの考え方」が生まれました。
一つの考え方は、「心が横道に逸れてしまったり、彷徨ったりしないように、心を一点に集中していられる持続力」を付けることで、「集中力」を高めようとするものです。これは:
- 「心と言うものは、逸れたり彷徨ったりしやすいものだから、逸れたり彷徨ったりしないで、一点に集中していられる時間を長くできるように、自分を鍛え上げていこう」とする考え方です。
もう一つの考え方は、「集中しているとは何か?」と言いう問いに対して、次のように考えた人たちによってもたらされたものです。それは:
- 「何か一点に気持ちや心を向けていても、気持ちや心は彷徨ったり逸れてしまったりするものである。そうであるなら、そのような心の動きを受け入れよう。そして、気持ちや心が集中した状態から逸れてしまったときに、そのような自分の状態になるべく早く気づいて、逸れてしまった気持ちや心を『集中していた“最初の一点”のところ』に戻して、そこに心を再び向ければよいではないか。そうすれば、集中できずに気持ちや心が彷徨っている時間が短くなり、結果的に気持ちや心が一点に集中している時間が長くなるのだから」と言う考え方です。

ここまでをまとめましょう。「瞑想の世界」では、「集中する」と言う考え方で、「2つのグループ」が出来上がりました。それは:
- 「集中している時間を、なるべく長くすることによって、集中している状態を維持し、集中力を高めようとしたグループ」…「サマタ瞑想」
- 「集中が途切れて気持ちが逸れたら、逸れてしまったことに早く気づいて、元の集中した状態に戻し、集中していない時間を短くすることで、結果的に集中してる時間を長くし、集中力を高めようとしたグループ」…「ヴィパッサーナ瞑想」
仏教や東洋思想がブームになったアメリカ合衆国で、この「ヴィパッサーナ瞑想」を医療の世界に取り入れた人物が、ジョン・カバット・ジンです。
彼は疼痛で悩む患者に対して、この瞑想法を指導したところ効果があることを発見し、それを「マインドフルネスストレス逓減法」してまとめました。
さらにこの考え方が「認知療法」に取り入れられ、「第3世代の認知療法」と言われる「マインドフルネス認知療法」へと発展しました。
「マインドフルネス」の魅力とは…。
「集中させる方法」して、「ヴィパッサーナ瞑想」では、「気持ちや心が彷徨い始めたりしたら、そうなっている自分に早く気づき、その自分を最初の気持ちが集中していたところに戻す」と考えました。この考え方の「ポイント」はどこにあるのでしょうか。
一つは「気づき」です。「心とは彷徨うものである」と言うことを前提にして、心が集中から逸れてしまったら、それに早く気づいて、最初の集中に戻すわけですから、心が逸れたことへの「気づき」を重視しています。そのため、「ヴィパッサーナ瞑想」を「気づきの瞑想」や「洞察瞑想」と呼んだりもします。
さらに、もう一つあります。それは「最初の集中に戻す」と言うことです。ただし、ここで注意が必要です。「“最初の集中”と言うのであれば、その日瞑想修行を始めたときの、“過去のあの時点”なのか?」と考えてしまいがちです。しかしそうではありません。
この「戻る場所」こそが「今ここ」なのです。この点が一番大切な「ポイント」です。
「マインドフルネス」を「現在において起こっている経験に注意を向ける心理的な過程」と定義しているように、集中できずに逸れてしまった心を、「もとに戻す場所」こそ「今ここ」なのです。

疼痛に悩まされている人は、できれば「痛み」のことなど考えたくないはずです。しかし、どうしてもその痛みに自然と意識が向いてしまいます。
こだわりが強い人や悩みを抱えている人も同じです。「もうそのことに、こだわることを止めよう」とか「悩みのことなど、考えないことにしよう」と思っても、ふと気づくと自分が止めようと誓った「こだわり」や「悩み」が気になってしまって、そのことが頭から離れないのです。
このような人たちに対する支援は、どうすればよいのでしょうか。そのための方法として、この「マインドフルネス」の考え方が、とても役立ちます。
支援は次のように行います。最初に「“今ここ”に意識を向けましょう」と指示を出します。最初は誰もが、確かに「今ここ」に意識を向けています。集中力が高いからです。
ところが、集中が途切れてくると、どうしてもそれぞれの人が抱える「痛み」「こだわり」「悩み」などに、自然と意識が向かってしまうものです。
このときに、自分の心を逸らしてしまったと自分自身を否定しないで、最初に指示された「今ここ」に、再び意識を向けるように指示を出します。
この「心が逸れたら、その状態に早く気づいて、“今ここ”に戻す」ことを、何度も繰り返すことで、結果的に心が「痛み」「こだわり」「悩み」などに向いていた時間が短くなり、反対に「今ここ」に留まっている時間の方が長くなってきます。
このように考えてみますと、「“マインドフルネス”とは、“今ここ”と言うことで、“心”が占められている状態」とも言えるのではないでしょうか。
「今ここ」とは、一体どこにあるのか?
「心が逸れたら、その状態に早く気づいて、“今ここ”に戻す」と言いますが、この「今ここ」とは、一体どこにあるのでしょうか。また、私たちは、「今ここ」にどのように気づけばよいのでしょうか。
「“今ここ”の気づきをどうするか?」と言うことが、「マインドフルネス」を実践する上では、とても重要な問題になります。
だれもが「今ここ」に気づける方法として、私は「呼吸」に注目しています。私たちが生きている限り、「呼吸」は必ず行われます。しかも、自分が呼吸していることを「体感」として気づくこともできます。
そのため、「今ここ」に気づく方法はいろいろありますが、私は「呼吸」を取り上げることが多いのです。

例えば、鼻から息を吸ったとしましょう。その時、まさに「今」あなたの鼻から息が入っていくことを、鼻腔に入ってくる外気の感触で、あなたは知ることができます。また、入ってくる外気によって、冷たさや温かさも感じ取ることができるでしょう。あるいは、鼻腔内がこそばゆく感じるかもしれません。
あなたが鼻から息を吸うという「今」の行為を、あなたは「今」、あなたの鼻が存在する「“ここ”の場所」で感じることができます。この瞬間あなたは、刻一刻と「今ここ」に留まっている自分を、あなたの「鼻」の部分に起きている変化とともに、実感することができるのです。
息を吐くときも、これと全く同じです。今度は鼻から「今」ゆっくりと息を吐いていきます。すると、鼻腔に沿って暖かい空気が「今」抜けていくのを感じ取れます。また、鼻腔内に少し湿り気を感じるかもしれません。あるいは、それまで吸った息で張り詰めていた胸やお腹のあたりが、「今」はゆっくりとしぼんでいくのが分かるでしょう。
「今」ゆっくりと息を吐く行為の一瞬一瞬を、あなたは「今」吐く息とともに、刻一刻と変わっていく身体という「ここ」で、確実に感じ取ることができるのです。
まとめ
私たちが「今を生きている」と言うことを、一列に並べられた「ろうそく」の中の一本に灯った「炎」が、隣のろうそくへと次々に移っていく「動き」として、視覚的に理解することができます。「今ここ」こそ「炎」の灯っている一本のろうそくなのです。
私たちは生きている限り「呼吸」を繰り返します。息を吸い込み、息を吐くことを繰り返すのです。自分の呼吸に意識を向けることで、自分自身に「今ここ」を気づかせることができます。
心が逸れてしまって、どこかを彷徨ってしまっていても、心配することはありません。「今ここ」に戻ってくるためには、自分の「呼吸」に意識を向ければよいのです。
私たちが生きている限り、私たちの「心」が戻ってくるべき場所を、「呼吸」は間違いなく私たちに教えてくれるのです。

このように考えると、「呼吸」と言う行為に意識を向けることは、彷徨いやすい「“心”の船」を、「呼吸」と言う「錨(アンカー)」に固定して、「“心”の船」が彷徨わないようにしておくための方法とも言えるでしょう。
「マインドフルネス」は、「今ここ」に自分が居ること、そして「今ここ」で自分が生きていることを、体感として自分自身に気づかせてくれる方法であると、私は考えているのです。

・1280.jpg)
